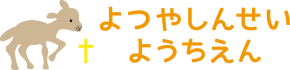今年度最後の保護者全体会。お話させていただいたことを書かせていただきました。振り返る時としていただけましたら幸いです。
さて、2018年度も残すところ3週間あまりとなりました。お祝い会を終え、この1年間の子どもたちの成長を感じていただくことができたと思っています。
初めて園生活をスタートした年少さんは、教師との友だちとの関わりに喜びをもつ姿に変わりました。お互いへの要求が強く出ている今は今後の年中さんでより深まっていくことでしょう。人のことが気になってしまう様子もお祝い会の中でも見られたのではないでしょうか。自然な姿です。年中さんになると自我も育ち、よりパワフルになります。そのことを悪いと思わずに成長として受け止めてあげてくださいね。
保護者の皆さまも子どもたち同様に初めての幼稚園での生活であったと思います。そんな中での幼稚園への理解とご協力に心より感謝いたします。この1年の経験をこれから新たに幼稚園生活をスタートしようとしている新入園児の保護者の方へぜひ支えとしてお伝えいただければ嬉しく思います。
年中さんは、グループや友だちとならできる。そんな姿があります。ですので、ひとりでの時との差が大きいです。それが悪いわけではありません、大切な気持ちです。今回のお祝い会での練習でもチームワークの良さを一番感じることができた姿でした。そして、見ていても分かるように恥ずかしいという気持ちがあるなかでよい表現であったと思います。
また、一人ではなく、友だちとならば強く表現できる姿。良いことも悪いこともです。気持ちが大きくなると言葉も行動も積極的になっていきます。自己表現することは大切なことです。とはいえ、度が過ぎるのはよくありません。年長に向かっていく中でここにしっかり向き合って残りの日々を過ごしていきたいと思います。また、保護者の皆さまも、とくに男の子は様々なことを考えつき、やってみようとします。やってみるまえに「それはだめ」「それはやったらどうなっちゃう?」などの声掛けはNGです。はっきり言います。聞いていません。保護者の方のイライラが増すばかりです。分かっていてもまずやらせてあげる。この気持ちを持ってあげてください。保護者の皆さまにはバザーなどで積極的に中心になっていただけたことに心より感謝いたします。
年長さんは、幼稚園をさよならするんだ。という気持ちが全体的に感じられています。今の年長さんは、聞き返すと、自分なりの考えを伝え、行動にうつすことができます。クラスの中では自然と深まっていますが、ちょっとクラスの枠から外れた時に、受け入れられなかったりする様子が見られます。団結力があることはよいことですが、自分たちが年長として、年少さんや年中さんにどのような関わり方をすることがよいのか。前に行くことだけでなく、時に引くことも必要です。そこを中心に3学期は特に力を入れて歩んできました。
23人がそれぞれの道に向かおうとしている今、周りへの気持ちにより意識が向くよう歩んでいきたいと思います。
また、ひとりで何かを任されて自分で行っていくということもクラスの中で深めています。自分で判断する経験を通して、自信をより深めて小学校へと歩みをつなげてほしいと思っています。
子どもたちはこれから大人が言わなくても、自然と卒園・小学校へと気持ちを向けていきます。そこで私たちができること。それはじっくり見守る。ということです。ここからは小学校に向けて何かを身につけたりする必要はありません。今までの積み重ねをもう一度振り返って行きましょう。そのことが何よりも子どもたちの安心、頑張りにつながっていきます。
私たちも、卒園までの取り組みでは新しいことを求めず、今のこの子どもたちの力がどのようにしていくことで発揮されるかということを第一に保育にあたっていきたいと思っています。
保護者の皆さまも残りの日々を思うと寂しさを感じることもありますが、今までの成長を噛み締める時間とすることで喜び合える時としてください。
また、先日の面談のなかで年長組の相談内容で多かったことが、ゲーム機の提供についてでした。今現在ゲーム機を使用している家庭、小学校になってからと考えている家庭、子どものうちは与えないと考えている家庭。様々です。当然です。そして、それで良いのです。
何が大切なのか。いつもお伝えしていますがここがポイントです。Aくんはお母さんにこう話したそうです。今までは、ゲーム機を持っていないのに、みんなにゲームのことを知っていること。やったことがあること。を伝えてきた。最近はどう?と聞かれれば、家にはないけどおばあちゃんのお家にあるからなかなかできない・・・。などと言ってきた。けれどぼくもう苦しくなちゃった。と。
皆さんはこの事を聞いてどう思われますか?
可哀想ですか。与えてあげればいいのになぁですか。当然、お母様もどうしたらよいのか悩みました。
しかし、このように言ってしまうA君の気持ち。よーくわかりますよね。私でもそう言ったかもしれません。
ここで大切なことは、Aくんがお母さんに気持ちをしっかり伝えられたことです。伝えられる成長をしてくれているということです。ここがポイントです。
みんなのことが大好きなんだね。よく言えたね。辛かったよね。話してくれてありがとう。その言葉でAくんはどれだけ救われるでしょうか。その上で、じゃあ、みんなと同じに買ってあげるね。ではなく、知らないことを知らない。もっていないないことをもっていない。ということが恥ずかしいことではないこと。いけないことではないこと。を伝えることができれば良いのではないでしょうか。
小学校へ行くと友だちとの関わりが広がり自然と家の行き来を通してゲームに触れる機会も多くなっていくことでしょう。そうして向き合い方を知っていけば良いのです。
今後の考えるうえでのひとつとしてください。
また、習い事をしている園児も多くいる中で、子どもたちが「いきたくない」「やめたい」と言うことがあります。道端でもそのようなやりとりをしている姿を見ることがあります。そこで親は続けることの大切さを優先し、「じぶんでやりたいと言ったのだから頑張りなさい」と言い、途中で投げ出すことが身につかないよう頑張ろうとします。これも幼児期では必要ありません。子どもたちがなぜやりたいと思うのか。単純な理由です。お友だちがいるから。ただやりたいと思ったから。なのです。やってみて嫌だった。ただそれだけのことです。習い事の場は、言葉のとおり、そのことを習う場です。ピアノであれば弾き方を。水泳であれば泳ぎ方を。が中心です。(すべてがそうと言っているのではありません。)ここも、ピアノって楽しいね。泳ぐことって楽しいね。を習います。という習い事に変わるといいなーと個人的に勝手に思っています。
世界で日本が幼児期に一番多い習い事はなんでしょう?・・・ピアノです。逆に大人になってピアノを弾いている人が少ない世界一も日本なのです。どういうことか分かりますか?・・・大人になるまでの間にやめてしまっている場合が多いということです。いかにさせられてになっているのか。さらに言うとピアノを楽しいと思って取り組んでこれなかった。ということです。途中で辞めざる負えなかった、続けられなかった理由ももちろんあると思います。
が、よくお母さま方の中にも「本当にピアノが嫌だった。苦しかった。」ということを耳にします。まさにそこです。(決して、ピアノや習い事を否定しているのではありません。ピアノを行うことで様々な面で成長や身につくことも多くあります。)
「やめていいよ。」と言う勇気を是非もってあげてください。今は、様々な経験をすること、吸収することが大切な時です。将来、選択肢が多くあるということは自分自身で考えるときには大きな余裕や可能性を広げてくれるものになることでしょう。全てをいい加減にと思うからそう思うのです。少しずつそのことを知っている時間なんだ。と思えば少しは違うのではないでしょうか。
逆に子どもがなぜ続けるのか?理由は簡単です。「すごいね!」と言われるからです。“すごい”ということは褒め言葉ではなく、子どもを余計に頑張らせてしまう言葉です。が、時と場合にはよりますよ。私たちも使うことがありますので。大好きなお父さん、お母さんにそう言われるからです。だから子どもたちは頑張るのです。まず、目の前のことに「できるとたのしいね。」「できることってうれしいね。」「できるまでずっとみていたよ。」「できたけどくるしかったね。」です。そうすれば、子どもたちは投げ出さず、自分で考えて判断できる人になっていきます。投げ出してもそこまで積み重ねてきたことが必ず力となって身についています。それが、親が望む子どもたちの姿になっていくことに繋がっていくのではないでしょうか。
小学校へと歩みを進める年長さんは特にここを大切にしてください。小学校へいくこと。そのこと自体がもう頑張っていることなのです。色々な小学校のやり方があります。そのことを守っていくことや従っていくことは大切ですが、そこに合わせた子どもたちを育てる必要はありません。これからも一人ひとりが違っていいんだ。もっとお子さまが持っている良い部分を見てあげてください。それがこれからの本人たちの力、武器になっていくのです。そして、更にそれが後に大きな違いとなって一人ひとりの姿となって現れてくることと思います。
最後に、今年度もまだ終わったわけではありませんが、大きな事故や怪我なく過ごせたことに心より感謝いたします。そして、多くのご理解とご協力に心より感謝いたします。残る日々も、保護者の皆さま自身が喜びを持ち、楽しむことを大切に子どもたちの前に立っていくことを願っています。