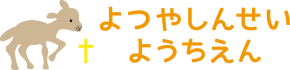今日は、2019年度初めの保護者全体会が行なわれました。
行事の説明を始め、園からのお願いなど、ご協力いただくことも多くありますが、子どもたち一人ひとりの姿を大切にこの1年も保育にあたっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
本日、はじめにお話させていただいた内容をもう一度書かせていただきたいと思います。ご参加できなかった皆さまも是非ご覧頂いてご理解いただけましたら幸いです。
改めまして、進級・入園おめでとうございます。
今年度は、幼稚園全体でもう一度、子どもたちにとって大切なことは何か。
子どもたちが楽しい、嬉しいと思えることは何か。子どもたちにとっての安心、安全とは何か。ということを見直しながら保育を行っていきたいと考えています。四谷新生幼稚園が大事にしている、キリスト教保育・自由保育の2本の柱を元にもう一度考えていきたいと思っています。
具体的には、子どもたち一人ひとりがそのままでいいんだ。と思えること。ここを大切にした保育を行っていく。ということです。もちろん今までもそのことを念頭に行ってきましたが、より子どもたちに寄り添った保育を考えていきたいと思います。
例えば、昨年度までは、運動会や芋掘り遠足の後には、振り返りとして楽しかったことを絵に描いて表現していました。絵を描くよ。と言われ全員が「やったー。」と思うでしょうか。もちろん描きたいと思う気持ちもありますが、他にも「どうやってかいたらいいかわからない。」「えなんてかきたくない」様々な気持ちがそこにはあります。その中で、そこに喜びや楽しみはあるでしょうか。そんなことをもう一度考えて保育を行っていきたいと思っています。
絵をやめるのではなく、絵を描くことの楽しさをもっと違う形で子どもたちに伝えていきたいと思っています。
次に、この1年間の子どもたちの成長について少しお話させていただきます。
幼児期の3年間は人間形成の一番大切な時と言われています。その中で子どもたちは生きる力を身につけていきます。生きる力とは自分で歩みだしていくことです。またそこには、必ず人と人との関わりがあります。楽しさも悲しさも関わりの中から生まれます。そして、自分の意見を言うことや、困難に立ち向かっていく強さをもっていきます。
しかし、それは突然身に付くものではありません。一歩一歩その子のペースで歩んでいくことで近づいていくのです。
では、どのような成長をしていくのでしょうか?
3歳は主体性が未発達な3歳と言われます。わかりやすく言うと、周囲のことが見えず、自分がこうと思ったらその思いを貫こうとする時期ということです。ですから、身近なものでは遊びますが、考えて作り出していくことはまだまだできません。思いの伝え合いができないことからものの取り合いをしたり、手が出たり、噛んだりすることもあるでしょう。しかし、そのことを怒るのではなく、その時の気持ちに十分寄り添ってあげてください。その上で、いけなかったことを話してあげてください。
あいさつができること、身の回りのことが自分でできること。それは大切なことです。しかし、今きちっとできているとしたら、決して良いことではありません。むしろ子どもたちはお母さんの表情を読み取り、こうすればお母さんが喜んでくれるから、こうしないとお母さんが怒るから。その気持ちを感じとって行っているだけです。そして、その姿を見て、大人は満足するのです。成長していると思ってしまうのです。それは、大きな間違いです。挨拶は、お母さんが行っている姿を見せてあげればいいんです。できることもやってと言ったらやってあげればいいのです。そこで、子どもたちが見て、気持ちを満たされることの方がこの幼児期には大切なことなのです。これは、小学校、中学校と進んで行った時に姿となって表れてきます。今の時期は、1回言ってできないことが当たり前と思ってください。
4歳は自己顕示欲の強い4歳と言われます。他人に自分を押し付けようとすることから、友だちとの間でぶつかり合うことが多く発生する時期であります。また、けんかの4歳とも言われます。ぶつかりあいを通して心の葛藤を育み、友だちに対してどう向き合ったらよいのかが分かるようになってくる大切な時期です。友だちと仲良くしたいがための成長だということをお覚えください。
生活にも余裕が現れ、良い意味で手を抜くことも増えることでしょう。そのような時は、こちらが望めば望むほど反対を向いていきます。こちらがそのことを分かり余裕をもって「そうね。」という気持ちで向き合っていきましょう。
5歳は他人が理解できる5歳と言われます。周囲の状況が見えてきて、友だちの存在が分かってくる時期です。個人ではなくグループへそしてクラス全体へと入っていきます。教師が介入しなくても、自分たちの力で何とかしようと考える力も育ってきます。ただし、お兄さん、お姉さんになったなー。と感じる反面、素直になれない部分もでてくるので、こちらからそのことに気づいて寄り添っていくことも大切になってきます。年中時に思い切り表現したことを年長クラスではしっかり締めるところは締め、思い切り行うことは力いっぱい表現する。といったことにもしっかり意識を向けていきたいと思います。
今まで話してきた中にはすべてにおいて、そこには必ず自分がいて相手がいます。これから幼稚園だけでなくご家庭でも、園外でも同じようなことがたくさん出てくると思います。そこで、保護者の方に大切にしていただきたいことは、その場の判断ではなく何かあったり、疑問に感じた時はまず、担任へ伝えてください。一番良くないことは間違ったことが飛び交ってしまうことです。例えば、「たたいたかもしれない。」ということが「たたいたみたいよ。」となって、「たたいたのよ。」となっていくことが子どもたちを一番惑わせます。怒られなくてもいいのに、嫌な思いをするのは子どもたちも保護者の皆様も同じことだと思います。その場合にはお母さん同士の解決ではなく、幼稚園での姿と重ね合わせながらお話ができたらと思いますので、どんな小さなこともご相談ください。よろしくお願いいたします。
また、特に年少保護者の皆さまはお母さま同士の関わりも初めての方もいらっしゃいます。
よく、隣の畑はよく見える。と言いますが、ここには十分意識して幼稚園生活を過ごしていただきたいと思います。何をお伝えしたいかと言うと、子どもたちの成長や姿はひとり一人違う。ということです。年少さんだから、男の子だからということは一切ありません。誰かが何かをできるようになると、「うちの子も」と思ったり「できていいなぁ」などと思ってしまいます。そして「うちのこだってできる」「うちのこにもそう言ってほしい」というような思いも出てくることも少なくありません。私はと思っている人ほど意外とそうなってしまうのですよ。
また、本を読んだりすると、いついつにはこれとこれが身につく。というように書いてあることがあります。ここも気にしない。です。人は何か基準がないと安心感や不安感のバランスがとれない生き物だと言われます。先の成長やできることを目標にするのではなく、目の前のお子さまの姿をしっかり受け止め、その時に必要な援助や道を作ることを大切にしてあげてください。
それがひとり一人違っていい。ということです。お母さま方もそのままのお母さまがたでいいのです。
悩んだ時や思いが溢れてしまいそうになった時にはいっしょに考えましょう。よろしくお願いいたします。